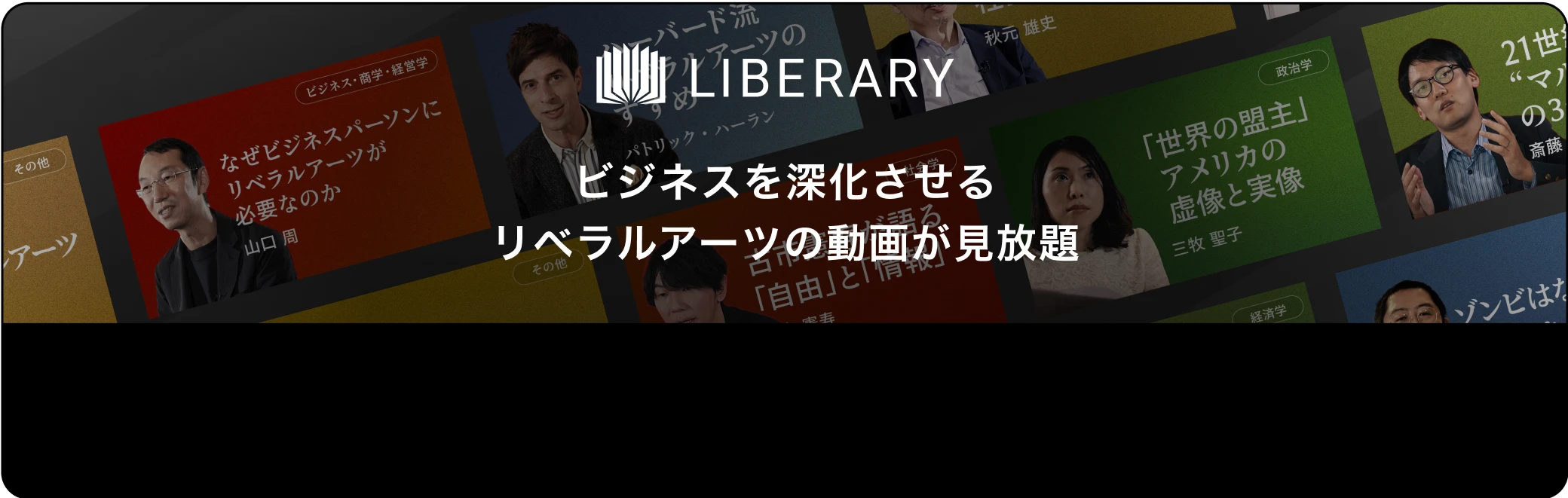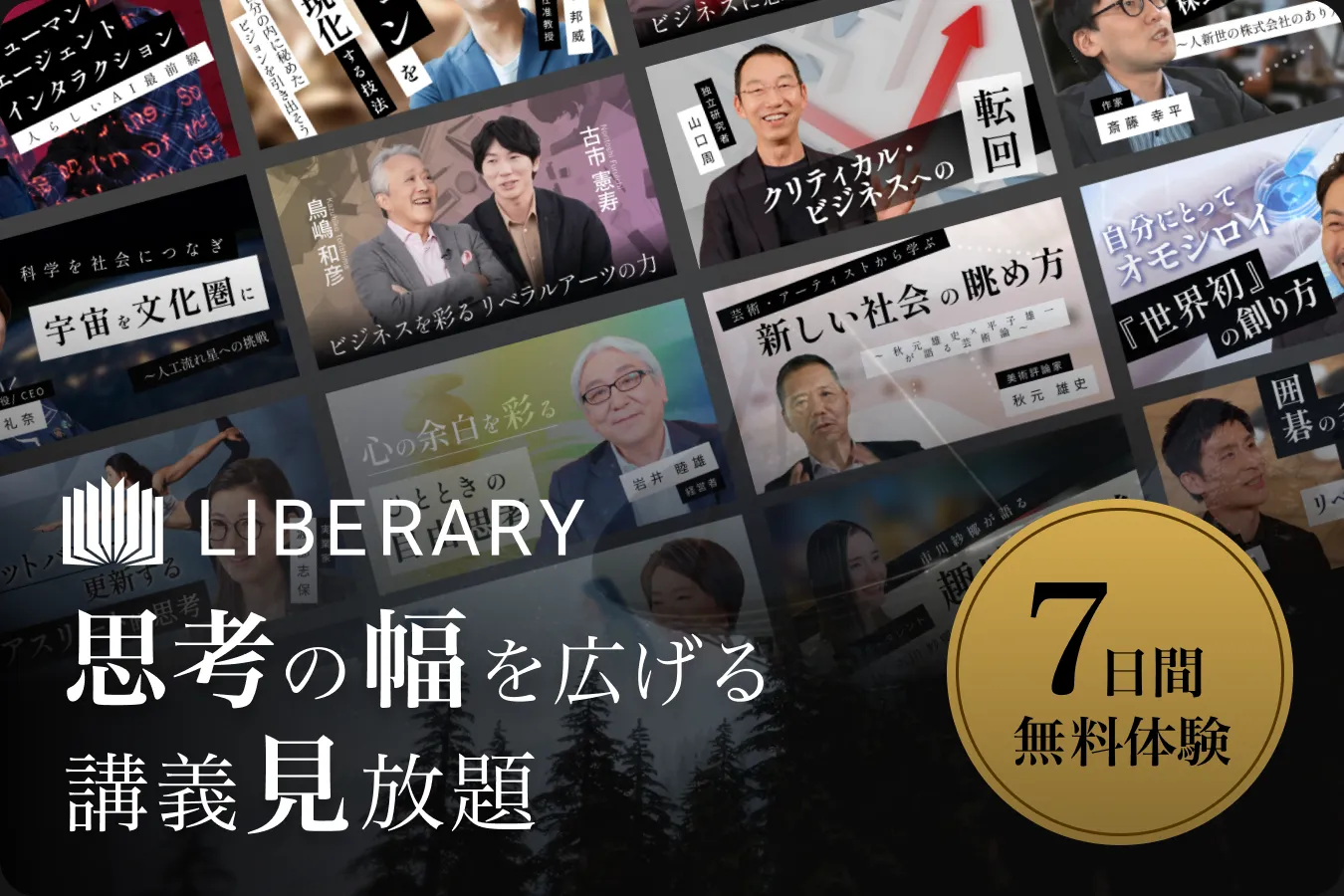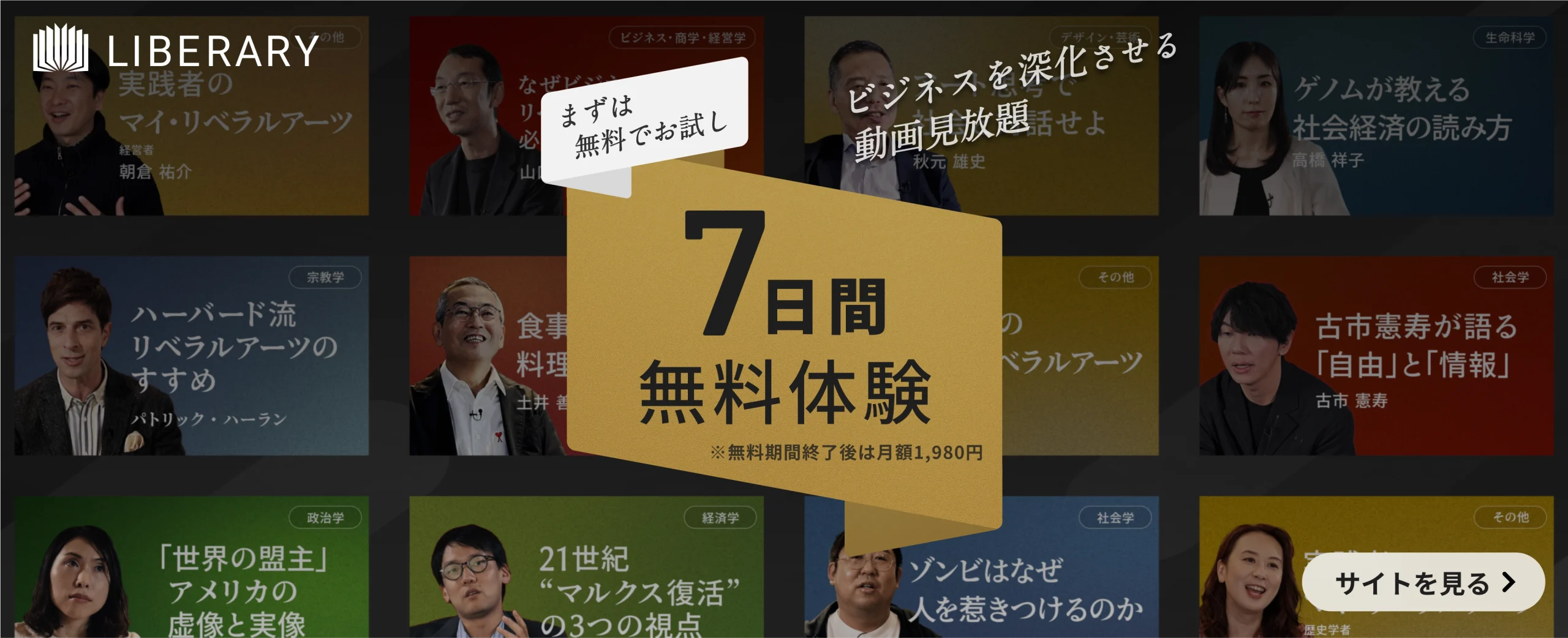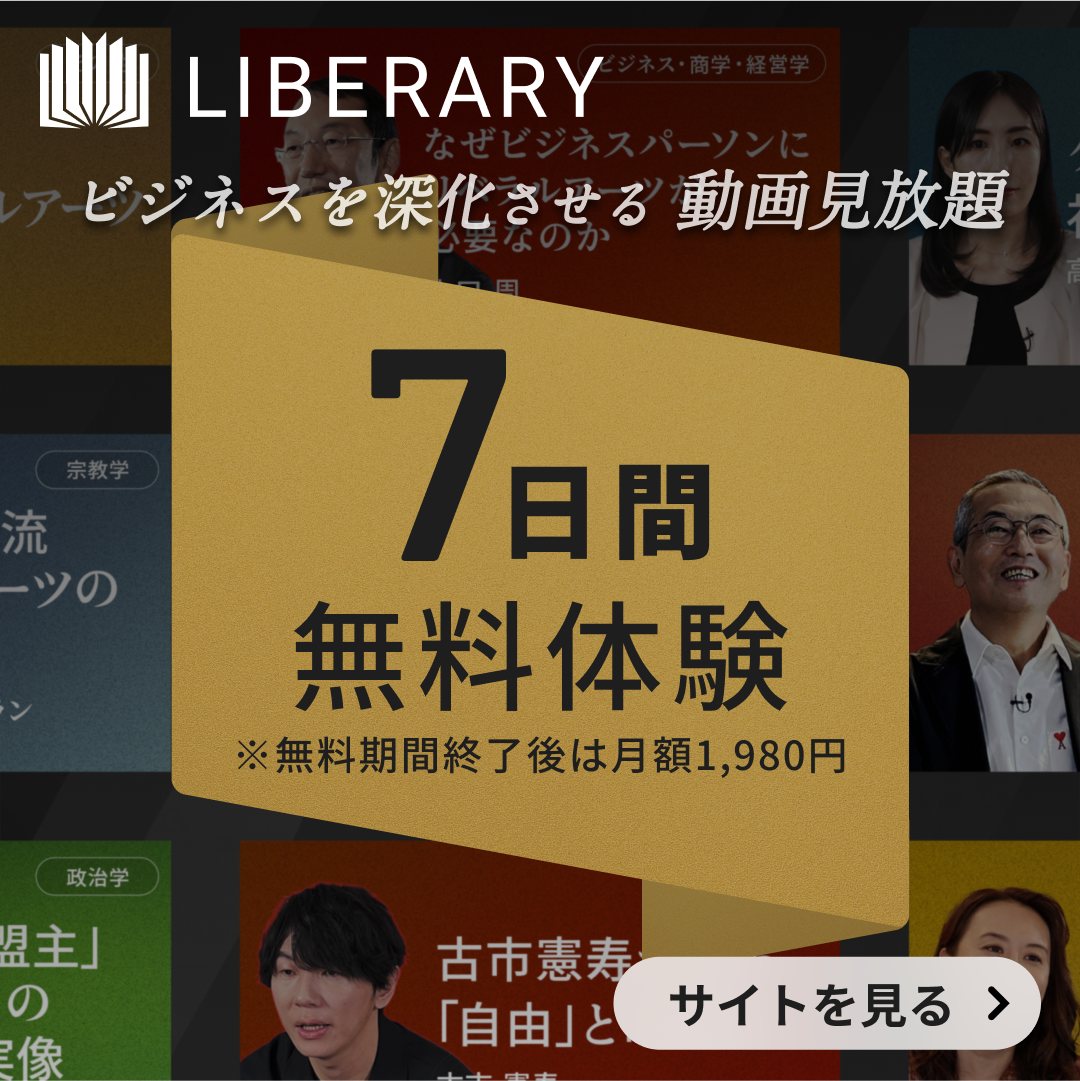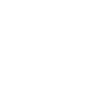ビジネスで「コミュニケーションを図る」ために「大切なこと」は?苦手を克服する実践スキル
導入:なぜ、あなたのコミュニケーションは「苦手」だと感じるのか?
もしあなたが、職場で「上司や同僚との会話が続かない」「会議での発言が苦手だ」「自分の意図が正確に伝わらない」といった悩みを抱えているなら、決して一人ではありません。多くの社会人が、日々のビジネスコミュニケーションにストレスを感じています。
「自分はコミュニケーションが苦手だ」と感じる主な原因は、コミュニケーションを「生まれ持った才能」や「雑談力」だと誤解していることにあります。しかし、コミュニケーションは才能ではなく、誰でも後天的に習得できる「技術(スキル)」です。
この技術を磨くには、まずその本質(大切なこと) を理解し、次に苦手意識を乗り越えるマインドセットを身につけ、最後に具体的な実践スキル(コミュニケーションを図る方法) を練習していくことが重要です。
この記事では、仕事におけるコミュニケーションの本質を深く掘り下げ、あなたが抱えるコミュニケーションの苦手意識を克服するためのマインドセット、そして職場で円滑にコミュニケーションを図るための実践的なスキルを具体的に解説します。
さらに、記事の後半では、コミュニケーションの応用力を高めるための「リベラルアーツ(教養)」の重要性と、その学習方法についても解説します。
本記事のゴール: コミュニケーションの本質(大切なこと)を理解し、職場で円滑に「コミュニケーションを図る」 ための実践的なスキルを身につける。
1. 【大切なこと】ビジネスコミュニケーションの目的と成功の土台
仕事におけるコミュニケーションは、単なる情報交換ではありません。それは「成果を出す」ための重要な手段であり、その成功の土台には「相手への関心」という大切なことがあります。コミュニケーション能力の本質は「流暢な話術」ではなく、「相手の意図を理解し、自分の意図を正確に伝える設計図を描く力」なのです。
1-1. ビジネスコミュニケーションが担う「3つの重要な役割」
ビジネスにおいて、コミュニケーションを図ることは、以下の3つの役割を果たし、組織や個人の成長に不可欠な役割を担います。
役割①:相互理解と齟齬の解消(ミスの防止)
最も基本的な役割は、誤解なく情報を伝達し、認識のズレをなくすことです。特にプロジェクトやチームでの作業において、指示や報告の意図が正しく伝わらなければ、作業の手戻りや納期遅延、そして致命的なミスに直結します。双方向のコミュニケーションを通じて、「わかったつもり」 ではなく、「完全に理解した」 状態を作り出すことが、高品質なアウトプットの前提となります。
役割②:信頼関係とチームワークの構築
日々の細やかなやり取り、特に非公式な会話や報連相の丁寧さこそが、信頼を生みます。信頼関係は、意見の対立が起こった際にも建設的な議論を可能にし、心理的安全性の高いチームを形成します。誰もが安心して意見を言える環境こそ、イノベーションを生み出す土壌となるのです。これは、ビジネスコミュニケーションにおける究極の目標の一つと言えます。
関連記事:信用と信頼の違いって?「信用はするが、信頼はしない」はどんな意味?
役割③:モチベーション維持と情報共有の活性化
上司からの適切なフィードバックや、メンバーへの感謝の言葉、そして情報の透明性のある共有は、個人のモチベーションを大きく左右します。情報がブラックボックス化すると、「自分は必要とされていない」と感じさせ、エンゲージメントが低下します。円滑なコミュニケーションは、組織全体のエネルギーを維持・向上させる役割を担います。
1-2. コミュニケーションを円滑にするための「心構え」
コミュニケーションを図る際、まず持つべき「心構え」は、小手先のテクニックよりも大切なことです。
「相手のために伝える」という意識を持つ(自己満足で終わらせない)
話す側は「伝えた」つもりでも、聞き手が理解できなければそれはコミュニケーションではありません。自己開示や情報提供は、あくまで「相手の理解を助け、相手の行動を促すため」に行います。この意識を持つだけで、話す前の準備(構成、言葉選び)が大きく変わります。
相手の立場や前提知識に合わせた言葉を選ぶ(専門用語の排除)
相手が新入社員なのか、経営層なのか、他部署の人間なのかによって、話すべき内容の粒度、使用する専門用語、そして話すスピードを変える必要があります。常に「この言葉は相手に通じるだろうか?」 と立ち止まって考える習慣をつけましょう。
結論から話すロジカルな思考の準備
特にビジネスコミュニケーションにおいては、時間効率が重視されます。まず結論(主張)を伝え、その後に理由や具体例を続けるロジカルな思考を準備することが重要です。これにより、聞き手は話の全体像をすぐに把握でき、ストレスなく内容を理解できます。
2. 【苦手克服】「コミュニケーションが苦手」を乗り越えるマインドセット
2-1. 「苦手意識」が生まれる2つの主な原因
なぜ、多くの社会人がコミュニケーションに壁を感じるのでしょうか。
原因①:過去の失敗経験や、HSP(繊細な気質)による不安
「以前、会議で発言して笑われた」「質問したら無能だと思われた」といった過去のネガティブな経験は、次の一歩を踏み出す際の強いブレーキとなります。また、他者の感情を敏感に察知しやすいHSP(Highly Sensitive Person)のような繊細な気質を持つ人は、会話中の相手の表情や沈黙を深読みしすぎてしまい、不安に苛まれることがあります。
【克服のヒント】 過去の失敗は、現在のあなたの能力とは無関係です。コミュニケーションは「打席に立った回数」が重要であり、失敗を「データ収集」と捉え直すことで、感情的な恐れを和らげることができます。
原因②:コミュニケーションを「完璧な雑談」だと誤解していること
多くの人が苦手意識を持つのは、「雑談」や「打ち解けた会話」です。しかし、ビジネスコミュニケーションの9割は、「報告・連絡・相談」「依頼・確認・質問」 といった定型的な情報伝達です。雑談のような完璧な「場つなぎ」や「ユーモア」は、必須スキルではありません。まずは、この定型的な情報伝達の精度を上げることに集中しましょう。これが上達すれば、自然と自信がつき、雑談への抵抗も減っていきます。
2-2. 誰でもできる!苦手な人が最初に取り組むべきスモールステップ
コミュニケーションが苦手な人が、いきなり流暢に話そうとするのは挫折の元です。以下のスモールステップから、成功体験を積み重ねていきましょう。
まずは「挨拶+一言」から始めるトレーニング(例:「おはようございます、今日も暑いですね」)
最も負荷の低い練習は、挨拶に天気や季節の話題など、内容に責任を伴わない一言を付け加えることです。この「一言」の目的は、「会話を始めるハードルを下げる」 ことと、「相手に自分への関心を示す」 ことです。毎日数人に対して試すだけで、「人とのやり取り」に対する心理的な壁は確実に低くなります。
話さなくていい:徹底して「聞く側」に回ることからスタートする
話すことが苦手なら、無理に話す必要はありません。まずは優秀な聞き手になりましょう。相手が話している最中に、意識的に以下の3点を行う訓練をします。
- ・アイコンタクト: 相手の目元か眉間を、話の区切りごとに2〜3秒見つめる。
- ・身体の向き: 相手に対して身体を少し傾け、関心を示す。
- ・相槌: 「へえ」「なるほど」「それで?」など、バリエーション豊かな相槌を打つ。
この姿勢は、相手に「この人は自分の話を聞いてくれている」という安心感を与え、自然とコミュニケーションを図る基盤となります。
相手の反応を気にしすぎない練習(失敗しても業務は回ることを知る)
会話中に相手の表情が少し曇ったり、沈黙が訪れたりしても、「自分のせいだ」「つまらない話をした」と結論づけるのはやめましょう。相手は単に何かを考えているだけかもしれませんし、別の業務で疲れているだけかもしれません。
「失敗しても業務は回る」「自分の一言で会社が傾くことはない」と割り切り、「今日の自分は一言話せた」という小さな成功にフォーカスすることで、次への意欲に繋げましょう。
3. 職場で「コミュニケーションを図る」ための実践スキル【インプット編】
ここでは、相手の情報を正確に受け取り、理解するための「聴く力(インプット)」を鍛える具体的な方法、すなわち傾聴力と質問力に焦点を当てます。このスキルが、あなたがコミュニケーションを図る上で最も大切なことです。
3-1. 聴くスキル:「傾聴力」を高める3つの技術
傾聴力とは、単に黙って聞くことではなく、相手に「あなたの話を受け止めている」と伝えるスキルです。
「うなずき」と「あいづち」 の効果的な使い方
- ・頻度: 相手が話し始めてから少し経って、内容が一段落する直前に打つのが効果的です。話のリズムを崩さないよう、過度にやりすぎないことが大切です。
- ・バリエーション: 「はい」「ええ」だけでなく、「なるほど」「そうなんですね」「それは大変でしたね」など、感情を込めた表現を混ぜることで、単なる聞き流しではないことを示します。
復唱(オウム返し) で相手に寄り添い、理解度を確認する
相手の言葉の要点や、感情を表すキーワードをそのまま繰り返す技術です。
- 例: 「納期が間に合わないかもしれません」 → 「納期が間に合わない、ということですね?」
- 効果: 相手は「自分の話が正しく伝わった」と感じ、安心感を得ます。また、こちら側も「解釈のズレ」をその場で確認し修正することができます。
相手の感情を推測し、言葉で返す「共感のフィードバック」
相手が言葉にしていない感情を汲み取り、それを言葉で返してあげることで、深い共感を示します。
- 例: 相手が難しい顔で資料を見せている → 「資料作成、かなりご苦労されたようですね」
- 効果: 感情の共有は信頼関係を飛躍的に高めます。特にビジネスコミュニケーションで、上司が部下の苦労を認める際に非常に有効です。
3-2. 質問スキル:相手の情報を引き出す「質問力」
適切な質問は、会話を途切れさせず、必要な情報を最短で引き出すための強力な道具です。コミュニケーションを図る上で、質問力は欠かせません。
はい/いいえで答えられる「クローズドクエスチョン」の適切な利用シーン
- ・定義: 答えが限定される(Yes/No、AorBなど)質問。
- ・利用シーン: 事実の確認や意思決定の促進、会話の軌道修正をしたい時。
- 例: 「この件の決定権はAさんで合っていますか?」
相手の意見や思考を引き出す「オープンクエスチョン」の活用法
- ・定義: 相手が自由に答える(Why, How, Whatなど)質問。
- ・利用シーン: 相手の考えや背景にある情報、アイデアを引き出したい時。
- 例: 「この改善案に至った背景を詳しく教えていただけますか?」
質問は一度に一つだけにする
質問を複数同時に投げかける(多重質問)と、相手はどの質問に答えるべきか迷い、混乱し、結果的に必要な答えを得られない場合があります。必ず質問は一つに絞り、相手の回答を待ってから次の質問に移りましょう。これは、コミュニケーションが苦手な人が焦って情報を得ようとしてやりがちな失敗の一つです。
4. 職場で「コミュニケーションを図る」ための実践スキル【アウトプット編】
インプット(聴く)ができた後、今度は自分の意図を明確に、かつ円滑に伝える「アウトプット」のスキルを磨きます。この伝えるスキルこそ、ビジネスコミュニケーションの質を決定づけます。
4-1. 伝えるスキル:誤解を生まない話し方のフレームワーク
自分の話が伝わらないのは、話す内容ではなく話す構成に問題があることが多いです。
結論ファーストを徹底する「PREP法」の使い方(Point, Reason, Example, Point)
PREP法は、コミュニケーションを図る上で最も基本的かつ強力なフレームワークです。
| 略称 | 意味 | 内容 | 役割 |
|---|---|---|---|
| P | Point (結論) | 最も伝えたい主張を最初に述べる | 聞き手の注意を引きつける |
| R | Reason (理由) | なぜその結論に至ったのか、根拠を示す | 結論の正当性・論理性を補強する |
| E | Example (具体例) | 事実、データ、過去の事例を提示する | 結論と理由をイメージしやすくする |
| P | Point (結論再提示) | もう一度結論を繰り返して、締めくくる | 強く記憶に定着させる |
特に、上司への報告や会議での発言は、必ずこのPREP法に沿って構成することで、あなたの発言が非常に論理的で分かりやすくなります。
「非言語コミュニケーション」を意識する(表情、トーン、身振り手振り)
メラビアンの法則が示す通り、人の印象は「言葉以外の部分」に大きく左右されます。
- ・表情: 微笑み(ミラーリング)は、相手の緊張をほぐし、親近感を生みます。
- ・トーン(声の調子): 早口は不安や焦りを与えます。大事なことは、いつもより少しゆっくり、低いトーンで話すことを意識しましょう。
- ・身振り手振り: 適度なジェスチャーは、話の内容に説得力とダイナミズムを加えます。ただし、過剰にならないよう注意が必要です。
関連記事:ノンバーバル・非言語的コミュニケーションとは?言葉以外の伝達方法を徹底解説
相手の理解度を必ず確認する「フィードバックの求め方」
伝える作業の最後のステップは、必ず「伝わったかどうかの確認」です。
- 悪い例: 「分かりましたか?」
- 良い例: 「ここまで説明しましたが、特に不明点はありませんか?」「念のため、ご認識の通りに内容を要約していただけますか?」
相手に要約してもらうことで、正確に伝わったかどうかを客観的に判断できます。これはコミュニケーションを図る上で、ミスの予防として最も大切なことの一つです。
4-2. ビジネスシーンに特化したコミュニケーションの応用
最後に、日々のビジネスコミュニケーションで直面する具体的なシーンでの応用スキルです。
報連相(ホウレンソウ) を効率化するチャット・メール術
現代のビジネスコミュニケーションでは、テキストベースのやり取りが増えています。
- ・件名: 「【至急・〇〇の件】結論:承認をお願いします」のように、件名に「結論」と「アクション依頼」を含めましょう。
- ・チャット: 箇条書きを徹底し、長文は避けます。一目で内容が理解できるよう、重要な部分は太字にするなどの工夫をしましょう。
依頼・指示を明確にするための「5W2H」活用
依頼や指示が曖昧だと、部下や同僚は迷走し、コミュニケーションが苦手な人は特に質問できずにミスを犯します。以下の要素を必ず含めて指示しましょう。
- 5W: Who(誰が)、What(何を)、When(いつまでに)、Where(どこで)、Why(なぜ)
- 2H: How(どのように)、How much(いくらで/どれくらい)
この7要素を満たすことで、相手は迷うことなく行動に移ることができます。
ネガティブな情報を伝える際の効果的な伝え方(クッション言葉の利用)
- クッション言葉: 否定的な意見や、相手のミスを指摘する前に、「恐れ入りますが」「差し出がましいようですが」「ご気分を悪くされたら申し訳ありません」といった一言を挟むことで、相手の心理的な防壁を下げることができます。
- 「I(アイ)メッセージ」: 相手を非難する「あなたは〜」ではなく、「私は〜と感じた」という主語を使うことで、感情論にならず、建設的なフィードバックを促すことができます。
- 例: 「あなたはミスが多い」 → 「私は、このミスで〇〇というリスクが発生したと認識している」
5. 【応用力】コミュニケーションの土台を築くリベラルアーツの学び
これまで、具体的な技術(スキル)とマインドセットを解説してきましたが、コミュニケーション能力の真の土台は、教養と知性、すなわちリベラルアーツ(Liberal Arts) の学習にあります。
5-1. コミュニケーション能力を飛躍させる「リベラルアーツ」とは?
リベラルアーツとは、直訳すると「自由七科」であり、現代においては「専門知識を超えた幅広い教養」や「ものごとを多角的に捉え、本質を見抜くための知の体系」 を指します。具体的には、哲学、歴史、文学、心理学、芸術、経済学といった分野がこれに含まれます。
リベラルアーツを学ぶことの最大の大切なことは、多様な価値観と背景を理解できる広い視野を身につけられる点にあります。この広い視野こそが、以下の点でコミュニケーションの苦手克服に役立ちます。
- ・深い対話が可能になる: 知識の引き出しが増えることで、単なる業務連絡に留まらず、相手の興味や関心に合わせた話題を提供でき、信頼関係構築が容易になります。
- ・相手を深く理解できる: 歴史や心理学を学ぶことで、なぜ相手がそのような価値観や行動パターンを持つのか、その背景を推測できるようになります。
- ・論理的思考が磨かれる: 哲学や経済学の思考を通じて、自分の主張をより論理的かつ説得力のある構成で伝えられるようになり、コミュニケーションを図る質が向上します。
関連記事:
リベラルアーツとは?意味やAI時代における教養を身につけるための学び方を知る
多角的とは?意味と活用法、広い視野を養うメリットを徹底解説
5-2. リベラルアーツ学習におすすめのVODサービス「LIBERARY(リベラリー)」
リベラルアーツを体系的に学びたい社会人におすすめなのが、KDDI株式会社が提供するVODサービス「LIBERARY(リベラリー)」 です。
LIBERARYでは、各分野/学問の有識者による講義を通じて、幅広いリベラルアーツの知識を効果的に学ぶことができます。
LIBERARYの特徴
- ・多岐にわたる分野/学問: 哲学、歴史、文学、心理学、芸術、経済学など、多岐にわたる分野の講義が用意されています。
- ・最新の知見: 単なる知識の習得を超えて、幅広く各分野の知識や最新の知見に触れることができます。
受講者の声が示す効果
実際にLIBERARYで学んだ社会人からは、コミュニケーションについてのポジティブな声が上がっています。
- 「上司や部下との接し方に変化が起きた。社内・社外問わず、コミュニケーションの質があがっている。」
- 「広い視野をもつことで、業務や人間関係のストレス軽減につながった。」
体系的な学びを通じて、コミュニケーションが苦手という意識を根本から解消し、ビジネスに活かせる教養を身につけることができるでしょう。
6. まとめ:コミュニケーションは訓練で上達する「技術」である
本記事で解説したように、ビジネスで「コミュニケーションを図る」ために「大切なこと」 は、卓越した話術ではなく、「相手を理解し、尊重する心構え」 と、それを実行に移すための「具体的な技術」、そしてその土台となる「幅広い教養(リベラルアーツ)」 の三つに尽きます。
あなたが今「コミュニケーションが苦手」 だと感じていても、それは単にこれらの技術を知らないか、練習量が少ないだけです。
重要なのは、完璧を目指すことではありません。まずはこの中から「挨拶+一言」や「PREP法」など、最も抵抗の少ないスキルを一つ選び、一週間毎日意識して使うことから始めてみてください。小さな成功体験が、あなたの苦手意識を確実に打ち破り、自信へと変わっていくはずです。
コミュニケーションは訓練で上達する「技術」です。今日から実践を始め、職場で円滑なビジネスコミュニケーションを実現させましょう。