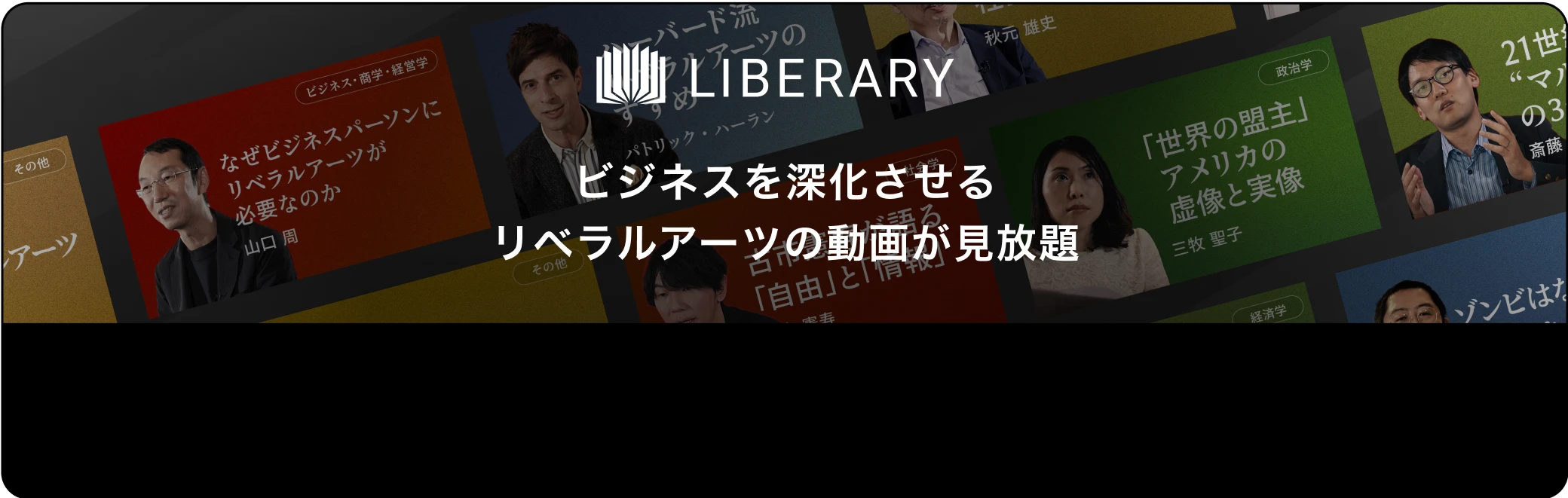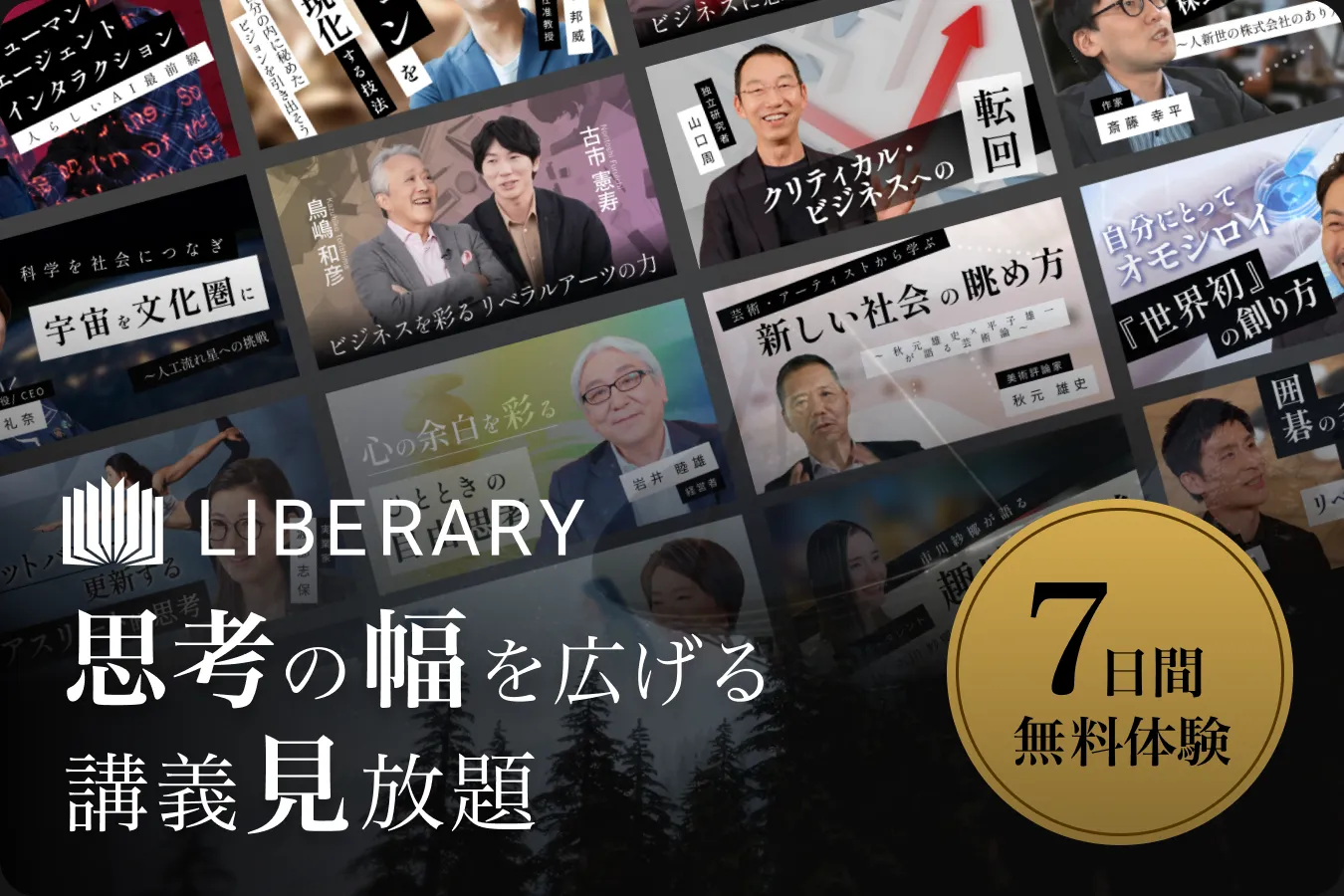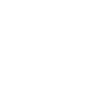モチベーションとは?意味や高め方、維持する方法を詳しく解説
モチベーションは、私たちの日常生活やビジネスシーンにおいて欠かせない原動力です。
高いモチベーションは個人の能力を最大限に引き出し、結果的に組織全体の成果向上にも貢献します。
一方、モチベーションが低下すると、生産性や創造性の低下、離職率の上昇など、多方面に悪影響が広がります。
本記事では、モチベーションの定義や影響、実際に役立つ方法論から、厚生労働省の調査データ、代表的な理論、そしてリベラルアーツ学習との関連に至るまで、多角的に解説していきます。
さらに、KDDI株式会社が運営する「LIBERARY(リベラリー)」など、具体的に役立つ方法もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. モチベーションとは
1-1. 基本的な概念
「モチベーション(motivation)」は、行動を起こすきっかけや維持するための心理的エネルギーを指します。
私たちが何かを始め、続け、目標に向かって進むときの“やる気”の源泉です。
- 内発的モチベーション
好奇心や興味、達成感など、自分の内側から湧き上がる動機づけ。長期的に持続しやすい傾向にあります。
例:「この分野が好きだからもっと勉強したい」「自分のスキルを高めたい」など。
- 外発的モチベーション
報酬や評価、罰など、外部からの刺激によって引き起こされる動機づけ。即効性はあるが状況によって変動しやすい特徴があります。
例:「昇進したいから成果を出す」「高評価をもらうために頑張る」など。
1-2. なぜモチベーションが重要なのか
モチベーションが高ければ、新しいことへのチャレンジや困難への対処が積極的になります。
また、学習意欲や創造性が高まり、結果として自分自身の成長だけでなく、組織や社会全体への貢献度も高まります。逆にモチベーションを失うと、日々の行動力や思考力が著しく低下し、生産性の低下や心身の不調を招く可能性すらあるのです。
2. モチベーションが与える影響
2-1. 個人レベルの影響
- 生産性・集中力の向上
高いモチベーションは集中力を持続させ、短時間で高いパフォーマンスを発揮することにつながります。
- 精神的健康のサポート
やる気がある状態は、ストレスをプラスに転換する力を高め、精神的な安定感をもたらします。
- 自己効力感の強化
「自分はできる」という感覚が強くなり、新しい課題にも恐れずチャレンジするマインドを育てます。
- キャリアアップの推進
モチベーションが高い人はスキル獲得や仕事の質の向上に前向きで、結果的にキャリアアップの機会が増えやすくなります。
2-2. 組織レベルの影響
- 組織全体の業績向上
モチベーションの高い従業員が増えれば、生産性が上がるだけでなく、組織全体に活気が生まれ、売上や顧客満足度にも好影響があります。
- イノベーション創出
新たなアイデアや革新的なサービス・製品開発は、モチベーションの高い組織文化が下支えします。
- 離職率の低下
従業員が「この会社で働き続けたい」という想いを強く持つようになり、結果として人材の定着率が向上します。
- チームワークの強化
相互に高め合う関係が築かれやすく、メンバー同士のコミュニケーションが円滑になるため、チームとしての成果が出やすくなります。

3. 厚生労働省の調査結果:雇用管理施策とモチベーションの関係
厚生労働省が2018年に実施した調査1(参照)では、企業が行う雇用管理施策の実施率と従業員のモチベーション向上に密接な関係があることが明らかになりました。
- 全体的な傾向
「長時間労働対策やメンタルヘルス対策」が93.6%と最も実施率が高い。続いて「仕事と育児との両立支援」が89.5%で、多くの施策で70%以上の実施率がある一方、最も低いのは「業務委託に伴う就業権の拡大」で51.4%。
- 人材マネジメント別の特徴
内部労働市場型企業:労働時間の短縮や働き方の柔軟化を積極的に導入
外部労働市場型企業:業務遂行に伴う裁量権の拡大を重要視
全般的に内部労働市場型が各施策の実施率をリード。
- モチベーション向上・低下による差
モチベーションが向上している企業の方が、ほぼすべての項目で施策の実施率が高い。特に「能力・成果に見合った昇進・昇格機会の提供」や「人間関係・コミュニケーションの円滑化」が明確に差を生み出す。
雇用管理施策が従業員のモチベーションに直接的な影響を与え、それが組織の成果や人材の定着に大きく関わることが、データからも読み取れます。
参考: 厚生労働省: 正社員の仕事に対するモチベーションの向上につながる雇用管理について
4. モチベーション理論の紹介・比較
モチベーションを体系的に理解するには、 代表的な心理学・経営学の理論を押さえておくと便利です。
4-1. マズローの欲求5段階説
アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した理論です。人間の欲求を「生理的欲求」「安全の欲求」「所属と愛の欲求」「承認の欲求」「自己実現の欲求」の5段階に分け、下位の欲求が満たされると上位の欲求に移行すると考えられています。
ビジネスへの応用例:基本的な給与(生理的欲求)や安定雇用(安全の欲求)を確保した上で、キャリア形成や自己実現の機会を提供することが従業員のモチベーションを大きく引き上げる。
関連記事: マズローの欲求5段階説を徹底解説!ビジネスでの活用方法も紹介
4-2. 自己決定理論(Self-Determination Theory: SDT)
人の内発的モチベーションを高める要素として、「自律性」「有能感(熟達感)」「関係性」の3つを重視する理論です。
ビジネスへの応用例:仕事の裁量権を与えて自律性を高め、スキルアップ支援で有能感を育み、チームビルディングなどで良好な人間関係を築くと、従業員のやる気が強く持続する。
4-3. ハーズバーグの二要因理論
モチベーションには「動機付け要因」と「衛生要因」の2種類があり、衛生要因は整っていないと不満を生むが、整っていてもモチベーションの向上に直接寄与しないとされます。一方、動機付け要因は直接的にモチベーションを高める要素です。
ビジネスへの応用例:給与や職場環境といった衛生要因だけでなく、仕事のやりがい・達成感・責任感などの動機付け要因をいかに高めるかが重要。
5. 具体的な事例・ケーススタディ
ここでは実際の成功・失敗事例を挙げて、モチベーション向上施策のリアリティを深めます。
5-1. 個人のケース:資格試験挑戦
仕事と並行して資格勉強をスタート。
・問題:開始直後にモチベーションが急低下。残業や家事で勉強時間を取るのが難しかった。
・対策:短期目標を1週間ごとに設定し、達成するたびにお気に入りのスイーツを食べるなど、小さなご褒美を導入。さらに、SNS上で同じ資格を目指す仲間と進捗を共有。
・結果:学習計画を細分化したことにより、やる気が持続し、半年後には目標の資格試験に合格。「自分はできる」という自己効力感も高まり、次のステップとして新しい資格にもチャレンジする意欲が湧いた。
5-2. 組織のケース:人事評価制度の見直し
あるIT企業が成果主義を導入したが、不透明さが原因でモチベーションが低下。
・問題:評価基準が曖昧で昇給・昇進のルールが分かりづらく、従業員の不満が続出。離職率も高まる傾向に。
・対策:目標管理制度(MBO)を徹底し、半期ごとにKPIを設定。評価プロセスを社内公表し、上司との1on1ミーティングを月1回以上実施。
・結果:評価の透明性が高まり、従業員一人ひとりが自分の目標達成に集中しやすくなった。半年後には離職率が明確に減少し、新規プロジェクトの成功数も増加。チーム内コミュニケーションも活性化した。
6. モチベーションを高める方法(個人レベル)
6-1. 明確な目標設定
・SMARTの法則:Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)
・具体例:「3か月後にTOEICスコアを700点にするため、毎日30分英単語学習+週末は模擬試験1回」など
6-2. 自己効力感の向上
・小さな成功体験を積む:1日のタスクを短時間で達成可能なレベルに分割し、達成感を得る
・成功日誌をつける:自分ができたことや良い習慣を日々記録する
6-3. ポジティブシンキング
・前向きワードの活用:「できない」より「どうすればできるか」を考える習慣
・過去の成功例の活用:苦しい状況に直面しても、「以前も乗り越えられた」という記憶を思い出す
6-4. 自己報酬
・ご褒美設定:目標達成時には特別な食事や旅行、欲しかったアイテムを購入するなど
・外発的モチベーションのブースト:内発的やる気だけではモチベーションが上がりにくいとき、報酬を使うと効果的
6-5. 学習と成長
・継続的なスキルアップ:資格取得や勉強会参加、読書などで新しい知識を吸収
・内発的動機づけ:「学びたい」「自分を高めたい」という気持ちが継続の原動力になる
7. モチベーションを高める方法(組織レベル)
7-1. 適切な評価と報酬
・評価制度の透明性:目標や基準が明確だと、従業員は不安や不満を感じにくい
・非金銭的報酬:職務拡大(ジョブローテーション)、スキル開発支援、社内表彰など多面的なアプローチ
7-2. 良好な職場環境の整備
・物理的環境:オフィスレイアウト、休憩スペース、リモートワーク環境など
・心理的安全性:失敗や意見に対して否定的な反応をせず、互いに尊重し合う組織文化を醸成
7-3. コミュニケーションの促進
・定期的な1on1ミーティング:上司と部下が目標や課題を共有し、解決策を一緒に考える機会
・チームビルディング:社内イベントやワークショップなどで部門や職種を超えた交流を図る
7-4. 自律性の付与
・裁量権の拡大:仕事の進め方やスケジュールを任せることで、責任感と内発的モチベーションを高める
・自主的なプロジェクト参加:従業員の意欲や得意分野を活かせる仕組み作り
7-5. ビジョンと価値観の共有
・経営理念の浸透:社内研修や全社ミーティングを通じて、組織の大きな方向性を明確にする
・「何のために働くのか」の再確認:自分の仕事が企業や社会にどのように貢献しているかを意識できるよう支援
8. モチベーションを維持する方法
8-1. 定期的な自己評価
・進捗チェック:週単位・月単位で自分の成果や課題を振り返り、修正する
・改善サイクル:Plan-Do-Check-Act(PDCA)を自分でも回す
8-2. 小さな成功の積み重ね
・段階的ゴール設定:大きな目標を複数のステップに分解し、少しずつ前進する
・可視化ツールの活用:目標管理アプリやカレンダー、ToDoリストで達成状況を“見える化”
8-3. ストレス管理
・運動・睡眠・食事:身体的健康がモチベーションを支える基盤
・マインドフルネスや瞑想:心を落ち着かせ、客観的に自分の状態を捉えるための方法として有効
8-4. 成長の可視化
・スキルマップや学習記録:どのスキルが向上したかを数値やリストで管理
・達成メモ:自分が努力して得た成果や気づきを定期的に記録し、自信を育む
8-5. サポートネットワークの構築
・メンターや同僚との交流:悩みや課題を共有することで適切なアドバイスや励ましを得られる
・SNSやコミュニティ:同じ目標や趣味を持つ仲間と意見交換できる場
8-6. 定期的なリフレッシュ
・有給休暇の活用:心身を休めるだけでなく、新しい発想を得る機会
・趣味や娯楽の時間:仕事とは別の楽しみを持つことでバランスを取る
9. モチベーション低下の原因と対策
9-1. よくある原因
- 目標の不明確さ:何を達成すべきかが曖昧だと行動の方向性を見失いやすい
- 過度なストレス:タスクオーバーや対人関係のトラブルがストレスを増大させる
- 成果が見えない:努力が認められない、または評価制度が不透明でモチベーションを失う
- 環境の変化:急な異動や生活習慣の変化に対応できない
- 自己効力感の低下:失敗経験や周囲からの否定的フィードバックで自信を喪失
- マンネリ化:同じルーティンや作業の繰り返しで新しい刺激を感じられなくなる
9-2. 具体的な対策
- 目標の再設定:小さく具体的な目標に分割し、達成感を得やすくする
- ストレス管理:専門家への相談や運動、休養を十分にとり、精神的負荷を軽減
- 成果の可視化:達成度を“見える化”し、自分が進んでいる実感を持つ
- 環境のサポート:上司や同僚に状況を共有し、業務量や仕事内容を調整する
- ポジティブな自己対話:「失敗は成長のためのステップ」という認識を育む
- 新しい挑戦の導入:仕事やプライベートに新鮮な要素を加え、やる気を刺激
- コミュニケーション強化:自分一人で抱え込まず、チームや家族と協力して問題解決を図る
- ワークライフバランスの改善:適度に休みや趣味を楽しむことで心身の疲労を回復
10. よくある間違い・落とし穴
- 高すぎる目標設定:達成困難なゴールを掲げると挫折感につながりやすい
- 外発的報酬への依存:評価や報酬だけが目的になると、報酬が減った途端にモチベーションも急降下
- 完璧主義:些細な失敗を許せず、必要以上にストレスや不安を抱えこむ
- 間違ったPDCA:形式的な振り返りだけで、実質的な改善策が打ち出されない
- 自分の強みや興味の軽視:本来好きなこと・得意なことを活かせない環境で無理に頑張るとモチベーションが枯渇しやすい
11. リベラルアーツ学習とモチベーション
リベラルアーツとは、文学、哲学、歴史、社会科学、自然科学など幅広い分野の教養を総合的に学ぶことです。
現代のビジネスシーンでも「複雑な課題を多角的に捉え、柔軟に解決できる力」が求められています。
現代のビジネスシーンでも重要性が増しています。
関連記事:
リベラルアーツとは?現代社会で求められる教養を身につけるための学び方
多角的とは?意味と活用法、広い視野を養うメリットを徹底解説
11-1. リベラルアーツ学習のメリット
- 異なる分野の知識を組み合わせることで、イノベーションや独創的なアイデアが生まれやすくなる
- 内発的モチベーションの向上:学びの楽しさを感じることで、継続的な自己成長意欲が高まる
- コミュニケーション能力の強化:文学や言語などを学び、言葉選びや思考整理のスキルが磨かれる
- 自己理解の深化:哲学や心理学の知見から自己を客観視し、自分の価値観や目指す方向を明確にできる
11-2. ビジネスパーソンにとっての意義
- 幅広い視野が経営判断や戦略策定に活かせる
- 多文化理解や多様性の受容能力が高まる
- チーム内外での議論に深みが生まれ、協働が促進される
12. 実践を助けるサービスの紹介:LIBERARY(リベラリー)
ここでは、KDDI株式会社が運営するリベラルアーツ学習サービス「LIBERARY(リベラリー)」をご紹介します。
個人向けと法人向けがあり、この記事では法人向けの「LIBERARY(リベラリー) for Biz」について記載します。
12-1. LIBERARY(リベラリー) for Bizの特徴
KDDI株式会社が提供する法人向け人材育成サービス「LIBERARY(リベラリー) for Biz」は、リベラルアーツの考え方を取り入れた革新的なサービスです。現代のビジネスリーダー育成における課題に対応し、多角的な視点からの議論や意思決定を促進します。
「 LIBERARY(リベラリー) for Biz」の特徴として、知のフロントランナーによる動画見放題サービスがあります。ビジネス、テクノロジー、人文科学など幅広い分野をカバーし、420本以上(25年2月時点)の独自撮り下ろし動画を配信しています。これにより、効率的かつ効果的な学習が可能となります。また、ビジネスリーダー向けの研修サービスもあり、より学習を深めることができます。
これを活用すれば、業務に直結する専門知識だけでなく、教養や広い視野を身につけ、長期的なモチベーション維持や内発的なやる気の創出が期待できます。
講義一覧は、こちら。
13. よくある質問(FAQ)
Q1: モチベーションが続かない場合の対処法は?
- 小さなステップの設定:1日の目標をあえて低めにして、達成の手応えを得る
- 仲間やコミュニティの活用:SNSや勉強会で進捗を報告し合う
- 自己報酬:目標達成でご褒美を用意し、行動を肯定的に捉える
Q2: 他人(部下や同僚)のモチベーションを上げるには?
- 具体的・積極的なフィードバック:成果や努力を分かりやすい言葉で称える
- 成長機会の提供:スキルアップ研修や新しいプロジェクトの参加を促す
- 当事者意識を高める:プロセスや判断に参画できるよう工夫する
Q3: モチベーションと生産性の関係は?
- 密接な相関:モチベーションが高いほど集中力が増し、仕事の質とスピードが向上
- 注意点:やる気の過度な高揚が燃え尽き症候群を招くこともあるため、適切な休息が必要

まとめ
モチベーションは、私たちの行動や成果だけでなく、人生全体の幸福感にも大きく影響する重要なエネルギーです。
まず、その本質としては「内発的モチベーション」と「外発的モチベーション」の両方を理解し、自分の中から湧き上がる興味や関心と、評価や報酬などの外部要因をバランスよく活用することが鍵になります。個人レベルでモチベーションを高めるには、小さな成功体験を重ねることや適切なフィードバックを受ける機会を作ることが有効です。また、組織としても評価制度や職場環境を整え、従業員の内発的なやる気を引き出す仕組みを構築することで、生産性の向上や離職率の低下につなげることができます。
厚生労働省の調査でも、長時間労働対策やメンタルヘルス対策などの雇用管理施策の実施度合いが、従業員のモチベーションに大きく影響することが示されています。これは、組織が職場環境や評価制度などを積極的に整え、個々人が仕事を通じて成長できる安心感を与えているかどうかが、モチベーションの高まりに直結することを裏付けています。
さらに、リベラルアーツ学習は自分の視野を広げ、思考の柔軟性や創造力を育むための効果的な方法です。
文学や哲学など一見ビジネスとは直結しない知識が、実は新しい発想を生むヒントや多面的な問題解決の視点として役立ちます。KDDI株式会社が運営する学習サービス「LIBERARY(リベラリー)」などを活用すれば、忙しい合間でもオンラインで多岐にわたる学問の講座を受けることができ、内発的なモチベーションを高める一助となるでしょう。
最後に、モチベーションを継続するためには、自分が「何のために」「どんな目標を持って」取り組むのかを明確にすることが欠かせません。小さくても達成しやすい目標を積み重ね、成功体験を可視化しながら、自分や組織の方向性を定期的に見直してみてください。モチベーションは「やる気」という単なる気分ではなく、人生のさまざまな場面で成果や幸福感を左右する大切な要素です。この記事をきっかけに、自分自身や周囲のモチベーションを高め、より良い未来に向かって一歩を踏み出しましょう。